非常に読みやすい写真の入門書
一般的な写真の教科書とは違って、写真を撮るときの心構え、とでもいうべき本。
HowではなくWhy、なのかもしれない。
教則本ではなく、写真を撮る自分のありようについての本、といってもいいかもしれない。
・写真は考える仕事
・写真を撮ることは簡単だが、誰にでも向いているものではない
・好奇心が旺盛・行動力がある人
・うまい写真がいい写真であるわけじゃない
・いい作品は見た人に感情が伝わるもの
・うまさを目指さない方がいい
・技術論を結局還元すれば1:光を読む技術、2:適切な距離感、3:レンズの選択
・どう思って写真を撮ったか、伝わってしまう。自分が好きなのか、被写体が好きなのか
・家族の撮った写真にケチをつけるのは作った料理にケチをつけるのと一緒。デリカシー必要
・子どもの楽しさを写真で邪魔しない
技術論的なことをいえば、
・三分割構図とかあまり考えず、しっかり中心で撮る(トリミングすればいい)
・写真に大切なのは写真以外の知識と経験
・ミックス光はよくない。
・会話の距離と撮影の距離は違う
・写真のために社会は用意されているわけではない(撮ってやってるではなく撮らせてももらう)
・RAWで撮れ(RAWで撮った写真はパソコンで現像作業が必要だが)
・その場で写真の確認をしない
・うまい写真の打率は、どんなにヘタでも3%くらいはある。なら数をとればいい
・カメラを買うときには臭いと、バッテリーが膨らんでいないかチェック
・とりあえず標準の単焦点レンズから
・オートにできることは全部オートにして撮影に集中する
・データの保存:最良なのはRAID
・家族写真をとるときに「目線を下げた」写真にこだわることはない
なんですかね、ジャズに例えると、楽典などの理論書ではなくて、
Jazzlifeの記事とかの「ソニー・ロリンズに演奏について訊いてみた」みたいな感じ。
ナラティブで、とても読みやすいし、写真をやっている人にとってはヒントがたくさんあるんじゃないかと思う。
自分の段階によって何度も読み返したら印象がかわるような気がする。
僕は写真はやっていないから、伝わるところはちょっとなんだけど、RAWで撮ってLightroomで現像する環境を考えてみようかな。















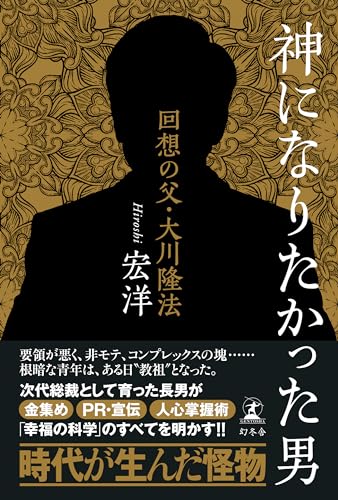











![[ホカオネオネ] スピードゴート 5 ゴアテックス 1127912 トレイルランニングシューズ メンズ US8.0(26cm) ブラック×ブラック [並行輸入品] [ホカオネオネ] スピードゴート 5 ゴアテックス 1127912 トレイルランニングシューズ メンズ US8.0(26cm) ブラック×ブラック [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41JkJo0QYwL._SL500_.jpg)

![[パタゴニア] M's Terrebonne Joggers メンズ テルボンヌ ジョガーズ 24540 SMOLDER BLUE(SMDB) [XSサイズ] [パタゴニア] M's Terrebonne Joggers メンズ テルボンヌ ジョガーズ 24540 SMOLDER BLUE(SMDB) [XSサイズ]](https://m.media-amazon.com/images/I/31MR7yPz9RL._SL500_.jpg)
![[ザノースフェイス] バーブライトランニングパンツ メンズ 撥水 ストレッチ 静電ケア アーバンネイビー L [ザノースフェイス] バーブライトランニングパンツ メンズ 撥水 ストレッチ 静電ケア アーバンネイビー L](https://m.media-amazon.com/images/I/31oGX8AsJlL._SL500_.jpg)
![[モンベル] アウトドア ジャケット 1101493 メンズ ブラック 日本 L-(日本サイズL相当) [モンベル] アウトドア ジャケット 1101493 メンズ ブラック 日本 L-(日本サイズL相当)](https://m.media-amazon.com/images/I/51GWsfv4mVL._SL500_.jpg)


